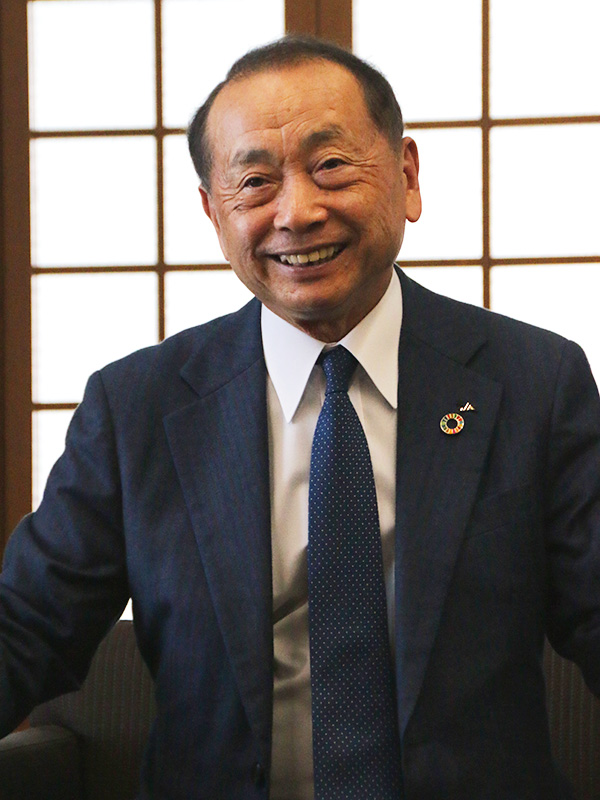地域農業47色
第6回 新しい広報のカタチと「基本」にこだわり、
次代につなぐ組織を
JAグループ福岡の取り組み
①福岡の食と農を、LOVEでつなごう
現地で開催してこそ伝わる農業情勢
■取り組み概要
JAグループ福岡では消費者からの理解を得るための取り組みとして、「食と農の応援団(食・農ラ部!)」をすすめています。
これまでJAが行なってきた小・中・高・大学生、地域住民などに対する食農教育活動を「食・農ラ部!」という統一名称を用いて、つなげることで、これまで以上に福岡の食と農の応援の輪を広げ、県産農畜産物の消費拡大、直売所の売上増に始まり、信用・共済事業の利用増、准組合員の加入促進へとつなげていくことを目的とした活動です。
またマスコミに対しては、これまでの定例記者会見に加え、生産現場に出向く現地記者会見を年に2回開催。福岡県の食と農業の現状をマスコミにしっかりと伝えるとともに、報道によって消費者への理解醸成につなげています。
「食・農ラ部!」についてはこちら
食・農 ラ部!について | 食・農 ラ部! (jashyokunolove.com)
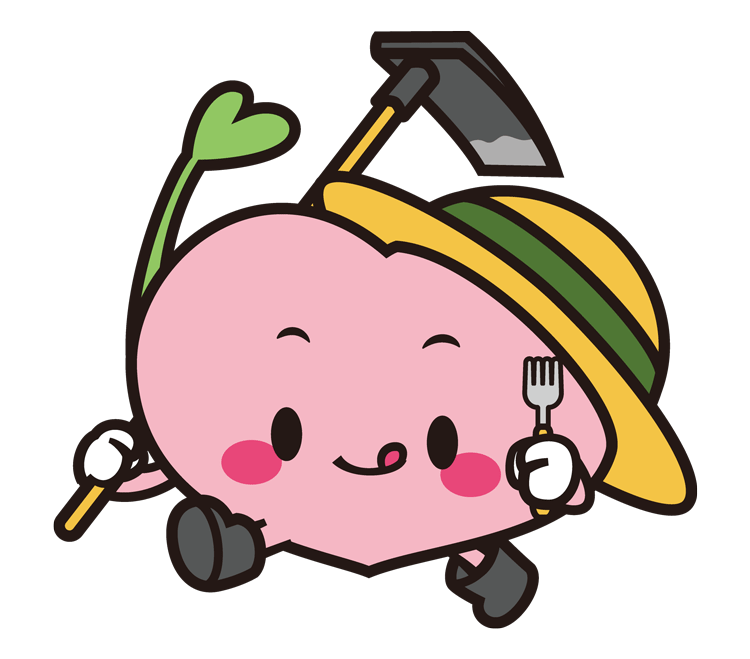
■JA福岡中央会の乗富幸雄会長より
JAは小学生を中心とした子どもたちや地域住民に向けて食農教育を実施してきましたが、これからは我々の取り組みを広範にわたって消費者に伝えていく必要があります。
特に福岡県は政令指定都市を2か所(福岡市、北九州市)抱えている一方で、農業もさかんに行われていて、生産地と消費地との距離がとても近いという特長があります。我々がもう少し努力することで、消費者との距離も近くなるのではないかと思います。
「食・農ラ部!」は福岡県の食のおいしさや農業の大切さにふれることで、心からのファンになってもらいたいという思いでスタートしたJAグループ福岡が展開する“部活動” です。食と農のセミナーや農業体験イベント、農業まつりなど、たくさんの活動を行っています。
部員になるとお近くの食と農に関するイベント情報や、お得情報、プレゼントキャンペーンなどの情報を配信しています。LINEで登録をしてもらいますが、登録者は13,000人を超えました。消費者の皆さんとの交流を深め、福岡県の農畜産物のおいしさを通じて食と農の大切さを知ってもらっています。


正直に言えば「『食・農ラ部!』って何だ」と最初は思いました。でも「ラ部!」の「ラ」には愛(ラブ)の他に、暮らし(ライフ)、大地(ランド)、研究室(ラボ)の3つの意味が込められていると聞いて、なるほどうまく名前を考えたなと感心しました。それに、デザインを見てみるとキャラクターもなかなか愛らしい。JAの事務所に行けば、いたるところにポスターが張られたり、窓口に飾ってある。何よりも皆が楽しそうで、全員でやっているという一体感を感じます。
食と農の大切さを伝えるには日頃からの取り組みが必要です。ふだんは距離を置いているような人にいくら言われたところで、いまひとつピンとこないですよね。消費者との距離を近づけるという意味でも「食・農ラ部!」の果たす役割は大きいと考えています。

また食と農への理解を深める取り組みとして、定例の記者会見がありますが、各連合会による合同記者会見の持ち方を会議室でやる一方的なものだけでなく、現地記者会見も加えることにしました。年に2回の開催で、記者には生産現場において直接、農業や農家の実情を見ていただき、それから会見に移る。トップが現場から伝えていくことが重要です。これまでの一方的な伝達から参加型の会見という、これからの広報のスタイルである双方向型を目指しました。
会見終了後には柿をもいだり、イチゴを摘んだりという収穫等のイベントも加えています。参加する記者からは「農家の現状がよくわかった」とたいへん好評です。
「食・農ラ部!」や現地記者会見は固定概念にとらわれず、みんなでいろいろなことに挑戦していくということ、その姿勢をトップが先頭に立って示していくことが重要だと考えます。
②組合員教育は喫緊の課題
福岡県全てのJAで組合員大学の開講を
■取り組み概要
JA組織においては、正組合員の高齢化と減少、准組合員の増加等、組合員構成の多様化がすすむ中、運営参加・参画の機会の少ない組合員の増加によって、組合員の顧客化や「わがJA意識」の低下が顕著に見られます。正・准組合員のメンバーシップ強化、とりわけ次世代組合員のリーダー育成は喫緊の課題です。
JAグループ福岡では、すべてのJAに組合員大学の設置を掲げ、次世代リーダーの育成と協同組合理念の共有に取り組んでいます。
■乗富会長より
実は私がいちばん力を入れたいのは教育です。JAの組合長時代に、今の組合員、特に若年層の中には、JAを業者くらいにしか思っていない人も残念ながらいることがわかりました。これではいけないと。組合員に対する教育、特に協同組合の理念の浸透等をしっかり行ってこなかったという反省を込め、教育の見直しをやろうと思いました。JAでは理事会や部会終了後に協同組合に関する動画を見てもらい、意識を高めようとしました。
中央会会長に就任後はこれを県下一斉に行おうと考え、中央会に教育部を独立させ、組合員教育に本格的に取り組むことにしました。これまでは職員教育をしっかりやっていれば、彼らが組合員教育もしっかりやってくれるという考え方から、中央会の教育センターで職員教育を中心に行っていましたが、それだけでは不十分である。やはり組合員への直接アプローチが必要であると考え、教育部を作り、職員教育だけでなく組合員教育にあたらせました。
まずは県内のすべてのJAに組合員大学の設置、できなければ協同組合講座の開講を目指しました。おかげさまですべてのJAでいずれかの取り組みをスタートするという目標を達成することができる見込みです。
カリキュラムは基礎的な内容からスタートします。たとえば「銀行とJAバンクとの違いについて」とかグループワークなどを行ってもらっています。まず初歩から始めて知識がついたら「組合員の中には、JAのことを悪く言ったり、批判をする人がいる。だが、協同組合、JAの仕組みなどを理解がすすめば、自分が所属する組織について悪く言うのは、自分自身の悪口を言っていることと同じである」と理解が進んでいきます。
基本をまずわかりやすく伝えていく、その段階が終了したら実際に参加してもらう。理論と実践を着実に実施していく。本の知識だけでなく、自分で考え、学ぶこと、聞くよりも見ること。そして行動すること。そのような機会を作ることが大事です。受講者からのアンケートにも「目から鱗が落ちるような思いだった」などと書かれてあり、たいへん好評をいただいています。
JAの組合長時代に、理事研修で東京に行くことを提案しました。でも研修のいちばんの目的で行ったのは神奈川県の小田原です。私の目的は小田原にある「二宮尊徳記念館」を視察することでした。「どうして小田原に行く必要があるのか」と言われましたが、視察終了後には「組合長が日頃から言っていることがよくわかった」という感想を参加者からはいただきましたよ(笑)。
これからも協同組合理念の理解醸成とリーダー育成を徹底してやっていこうという信念で取り組んでいきます。

全国のJAグループに伝えたいことについて乗富会長に伺いました
今年の秋にはJA全国大会、そして各都道府県のJA大会が開催されます。
JAグループ福岡は、目まぐるしい情勢の変化や組合員の多様化とさまざまなニーズに対応するため、引き続き不断の自己改革に取り組んでまいります。
JAは地域に根差した人の組織ですが、組合員構成が多様化し、JAに対する意識も自分の若い頃とは変化していますし、正組合員が減少し、組織基盤の持続性が問われていますが、JAがこれからも存続していくには組合員教育は喫緊の課題です。
また食・農・地域・JAへの消費者の理解醸成を深めていくためには、広報活動を経営戦略の重要な柱と位置づけ、対外広報の強化、特にこれまでの一方的な伝達とは違った、参加してもらう双方向型の広報の強化が重要となっています。
福岡県では「食・農ラ部!」の設置、組合員教育の見直しに取り組み、消費者の理解、組合員意識の変化に成果が出ています。協同組合の原点である「人づくり」に、全国各地のJAグループで積極的に取り組んでほしいと思います。