主食用米が高騰した「令和の米騒動」は日本人の米に対する意識を大きく変えた。米が足りないなら外国から輸入すればよいという意見が広まり、高い関税を払ってまでアメリカから輸入した「カルローズ米」が店頭に多く並ぶ事態になった。また、国内で米を増産し、余った分は積極的に輸出するべきだという意見も多く聞かれる。主食である穀物の需給バランスを外国との交易で調整することは果たして容易なのか。本書はその驚くべき先行事例を克明に描く。
本書のテーマである小麦も、米と同じく重要な食糧である。戦後、日本では小麦の消費が定着したが、自給率は戦前の100%超から現在は10%台にまで低下している。その背景にあるのが、アメリカ合衆国の食糧政策である。
1950年代半ばのアメリカでは、第二次世界大戦を挟む技術革新による生産量の増大、朝鮮戦争休戦による戦争特需の蒸発、2年続く世界的な大豊作により、小麦をはじめとする余剰農産物の処理が問題となっていた。こうした状況を打破するため、アイゼンハワー大統領の肝いりで、10億ドル規模の政府資金を投下し余剰農産物を処理する「PL480」という法案が成立した。外国への輸出を現地通貨建てで認め、借款として還元する仕組みである。
日本はこれを活用し、円建てで小麦を輸入し、多額の借款を引き出すことに成功した。国民の栄養改善を目指す日本は、この資金を活用して全国の農山漁村に粉食を普及させるため、うどんやパンの実食を行うキッチンカーを仕立てて各地を回る事業を行い、全国の主婦の胃袋をつかむことに成功する。さらに、大規模なテレビ広告による宣伝、全国のパン職人を対象とする研修会の開催など日本国内にアメリカ産小麦を定着させる素地を形成していく。また、安価なカナダ産小麦を排除するため、アメリカの小麦生産者団体は徹底したロビー活動を行い、アメリカ国内の鉄道貨物運賃の引き下げを実現し、価格競争力を高めてシェア奪還を果たす。このように、官民挙げた徹底した需要開拓を行うことにより、米食文化が根強い日本にアメリカ産小麦を定着させることに成功したのである。
食の外交には、官民一体となった国家戦略と文化戦略による、周到な用意が欠かせないことを本書は示唆している。
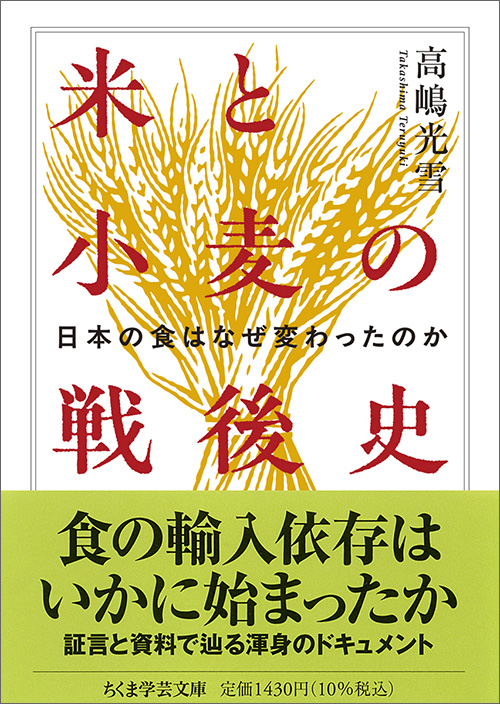
(評 JA全中広報部)



