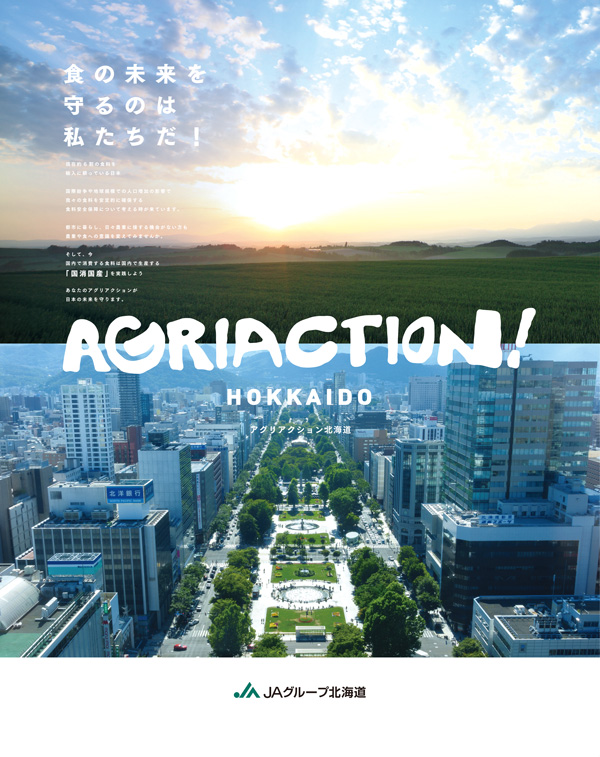地域農業47色
第39回 琵琶湖を守る営農の実践/農家所得増大へ新品種の導入も
JAグループ滋賀の取り組み
① 琵琶湖を守る営農の実践
■取り組み概要
琵琶湖の保全を意識した農業に長年取り組んできた滋賀県では、「環境こだわり農業」が根付いています。JAグループ滋賀は、安全・安心な農産物を生産する持続可能な農業を目指して、その推進を継続しています。2020年度からはオーガニック農業の拡大に向けても産地育成に乗り出しました。
■JA滋賀中央会の竹村敬三会長より
滋賀県では、県民全体が琵琶湖に対して強い思いを持っています。琵琶湖は滋賀のみならず京阪神地域の飲料水源であり、多様な生態系を育む日本を代表する淡水湖でもあります。
1977年に琵琶湖での赤潮が発生したことをきっかけに「石けん運動」と呼ばれる、リンを含む合成洗剤の使用を控える県民運動が広がり、JA女性部も積極的に運動を支えました。このように、県民一人ひとりが「琵琶湖を守る」という使命感と高い環境への意識が県民性として受け継がれています。
農業面においても、化学合成農薬や化学肥料の使用量を通常よりも削減するなど環境に配慮した「環境こだわり農業」として制度化されています。化学合成農薬と化学肥料を慣行の5割以下に抑え、濁水の流出防止など琵琶湖をはじめとする環境への負荷を削減する栽培は、手間がかかり、収益が減る場合も少なくありません。それでも、目先の利益よりも、環境と調和した農業を守り続けようという強い意志を持つ生産者が多いのではないでしょうか。
琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が2022年にFAO(国際連合食糧農業機関)の「世界農業遺産」に認定されました。これは「環境こだわり農業」や湖魚(ニゴロブナなど)が産卵・繁殖できる環境を整備した「魚のゆりかご水田米」などの営農の努力が評価されたものであり、今後も着実に継続していくことに意義があると考えています。次世代につなぐ観点から、学校現場で「琵琶湖システム」について学び、理解を深めてもらうことが重要です。
また、2020年度からは「環境こだわり農業」をさらに進めたオーガニック農業の推進にも力を入れています。米では県のオリジナル品種「きらみずき」が注目されており、オーガニック米として県域での生産拡大を目指しています。

② 農家所得増大へ新品種の導入も
■取り組み概要
農家所得の増大へ、JAグループ滋賀は高温耐性など県育成の品種の導入に加え、高収益作物の産地化や輸出も意識した取り組みを進めています。
■JA滋賀中央会の竹村敬三会長より
農家所得の増大に向けて生産振興を図りたいと考えています。滋賀県が地球温暖化による米の品質低下に対応しつつ、ブランド力ある産地づくりを目指して開発した「みずかがみ」は、今年で13年目を迎えました。24年産米の1等比率は86%と近年の猛暑下でも高品質を維持しており、日本穀物検定協会の食味ランキングで「特A」に認定されるなど食味でも高い評価を得ており、滋賀県を代表する品種として定着しています。
最近では、新品種である「きらみずき」の栽培も始まりました。これは化学肥料や殺虫・殺菌剤を使わずに栽培する品種で、「環境こだわり農業」をさらに発展させるものです。一部のJAでは、オーガニック部会を立ち上げるなど、組織的な取り組みが進んでいます。これまでの積み重ねがあるからこそ、さらなる高みを目指せると感じています。
米以外では、県育成品種のイチゴ「みおしずく」や、高収益が見込める「トレビス」(紫キャベツに似た葉物野菜)、そして国内外で人気の高いサツマイモの生産振興にも取り組んでいます。トレビスとサツマイモについては、JA全農しがに新設された生産振興課が集荷や販路開拓、販売などを担当しています。トレビスは取り組み開始から3年目を迎え、京阪神地域を中心に飲食店やホテルへの販路も拡大中で、生産現場としても手応えを感じており15ヘクタールまで生産拡大を目指しています。
サツマイモは香港などアジア圏で日本産サツマイモの人気が高いことを踏まえ、滋賀県産も輸出品目としても育てられれば大きな可能性を秘めています。輸出実績が1000トン近くになった米もそうですが、長期的な戦略としての輸出は不可欠ですので、重要な柱のひとつとしてチャレンジしていきたいと考えています。

全国のみなさんに伝えたいこと
私たちJAグループ滋賀は、生産者を支えるため、滋賀県と「農業振興に関する協定」を締結し、農業者の所得向上・経営の安定・農村地域の活性化に向けた取り組みを、行政と一体となって推進しています。この取り組みにより、滋賀の「食と農」、そして「農村社会」を次の世代へとつなげていくことを、大きな目標としています。
生産者を支えるために、再生産可能な所得の確保や、セーフティネットの構築、新たな品目提案による生産振興、スマート農業や省力化技術の導入支援など、現場の声を見逃さず、日々の業務に取り組むことの重要性を、あらためて実感しています。
新米が出回る時期になりました。生産現場では、農業経営の法人化が進む一方で、後継者不足という課題を抱えているのが実情です。作り手がいなくなれば、集約してきた田畑も耕すことができず、一気に耕作放棄地が増えてしまいます。また高騰する生産資材価格を農産物の販売価格に反映できずに農業者が自らの所得を削って何とか生産を継続している実情もあります。だからこそ私たちは、農業者の所得向上に向けた取り組みとともに、消費者の皆さまの理解と共感が何よりも力になると考えています。まずは、滋賀県産の農産物をJA直売所などで手に取っていただくことが、生産者の励みとなり、安全・安心でおいしい食にもつながります。これからも皆さまとともに、滋賀の農業と琵琶湖を未来へつないでいきたいと願っています。
ぜひ、京都のすぐ隣・滋賀県に足を運んでいただき、日本一の湖・琵琶湖のスケール、そしてそれを守るために育まれた滋賀ならではの農業と食文化を体験してみてください。