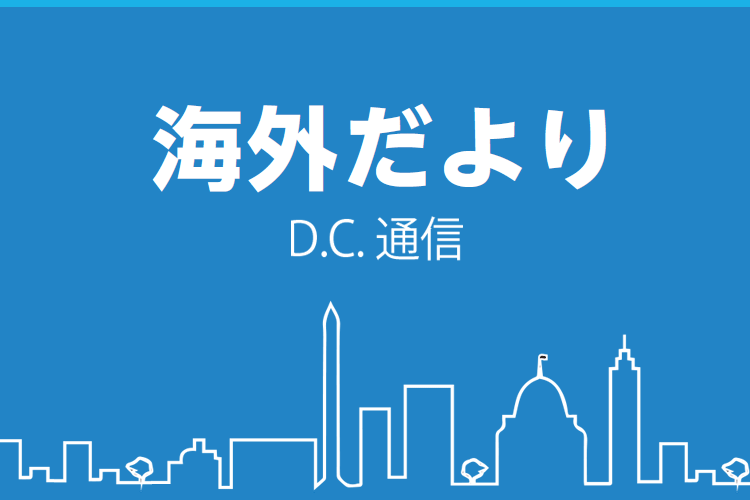H-2Aビザ
永住権のない非移民ビザにはいくつかの種類が存在するが、アメリカの農業経営者が外国人労働者を雇用する際に利用するH-2Aビザ(季節農業労働者向けビザ)プログラムは、1986年の移民改革統制法により創設された。H-2Aビザの主な特徴、雇用主に求められる要件等は以下の通りである。
① 労働力の必要性が季節的または一時的なものであり、期間が1年未満(通常10か月以内)であること¹
② 事前に国内でアメリカ人労働者の求人募集を行うこと²
③ 外国人労働者に対して、州や地方の最低賃金もしくは「悪影響を与える恐れのある賃金レート(AEWR)³」のいずれか高い賃金を支払うこと
④ 外国人労働者に対して、就労に必要な住居、交通手段、1日3食の食事または自炊できる場所・設備、出入国費用等を提供すること
国内の労働力不足を背景に、近年このH-2Aビザの利用が急増しており、国務省の公表によれば2022年は約29万8,000件のH-2Aビザが発給されている。これは5年前の2017年と比較して約1.8倍の件数に上る⁴。
先日のFarm Journal YOUTUBE CHANNELでは、H-2Aビザを利用して外国人労働者を雇用しているフロリダ州のスイカ農家が紹介された。この農場では、約220万個のスイカの収穫のために、150人以上の外国人労働者を約6週間雇用しているとのことである。この農場の外国人労働者は全てメキシコからで、また、この農場では労働時間の上限がないため、雇用期間中は好きなだけ働くことができ、1週間で1,000ドル以上を簡単に稼ぐことができるとの説明があった。
他方で、このH-2Aビザプログラムに関して近年特に問題となっているのは、上記③で示した賃金(AEWR)についてである。毎年政府が決定し、実質的な最低時給となるAEWRは年々上昇しており、2023年の全国平均値は16.13ドルと、2018年の12.47ドルと比較して5年間で約3割上昇している⁵。5月31日の上院司法委員会の公聴会で証言したサウスカロライナ州の農家であるChalmers Carr氏⁶は、AEWRの上昇が生産コストの上昇や食品のインフレ、諸外国の農産物との競争力の低下をもたらしていると述べている。
このほか、H-2Aビザプログラムに関しては、周年拘束性の強い酪農等での利用が難しいことや、複雑な事務手続き、申請にかかる費用などについて、農業団体等から見直し・改善を求める声が上がっている。
また、上記の通り、近年H-2Aビザプログラムの利用は急増しているものの、農務省の公表によれば、2020年時点で雇用農業労働者の41%は合法的な資格を持たない者が占めているとされ、いまだに不法移民が労働力を支えている実態もある。
1 農繁期の労働力不足等を念頭に置いた制度と言え、このビザで就労する者はゲストワーカーとも呼ばれている。
2 あくまでアメリカ人の雇用が優先であり、国内の労働力不足を証明することが求められる。
3 AEWR(Adverse Effect Wage Rate)は、アメリカ国内の同種の労働者の賃金を保護するために設けられている。
4 H-2Aビザの発給数に上限は設けられていない。
5 実際には州ごとにAEWRが定められており、2023年で最も高い州であるカリフォルニアのAEWRは18.65ドル、最も低い州は13.67ドルである。
6 アメリカ最大の農業団体であるアメリカン・ファーム・ビューロー・フェデレーション(AFBF)の労働委員会委員等を務めている。
深刻な労働力不足とワーキンググループの設立
幅広い移民関連問題に取り組む非営利団体のナショナル・イミグレーション・フォーラムが昨年11月に公表した記事によれば、アメリカは産業界全体で深刻な労働力不足に直面しているが、特に影響を受けているのが農業と食品産業であるとされている。
不法移民対策とあわせ、農業分野の労働力不足への対応が議会でも議論されているが、目立った進展はみられていない。2021年3月18日、一定の要件を満たす不法農業従事者に合法的な地位を与えることや、H-2Aビザプログラムの見直しなどを含む「2021年農場労働力近代化法案」が下院で可決されたものの、上院を通過することはなかった。
こうした中、本年6月21日、下院農業委員会のメンバーによる超党派の農業労働力ワーキンググループの設立が発表された。同ワーキンググループでは、関係者から意見聴取を行った上で、H-2Aビザプログラムの問題の解決策等を議論していくこととしており、具体的な成果につながるかどうか今後の動向が注目される。