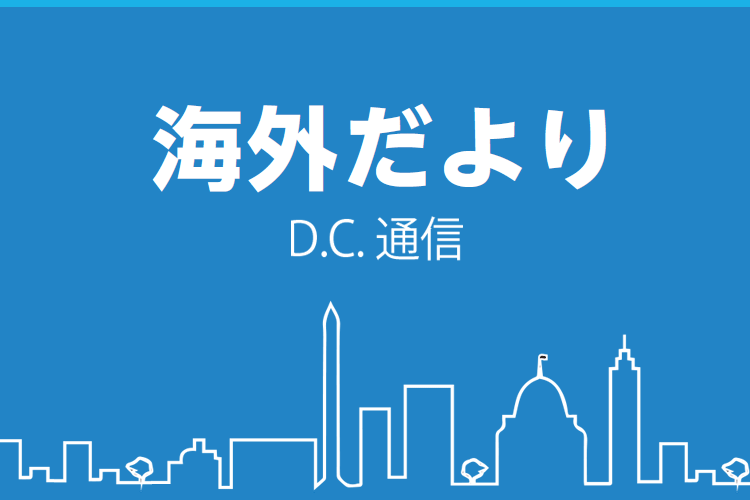日本でも秋の一大イベントとして定着しているハロウィーン。起源は、ヨーロッパの古代ケルト人が、ケルト暦の一年の終わり(10月31日)に、秋の収穫を祝い、死者の魂が現世に戻るとともに、悪霊を追い払う宗教的な行事といわれており、2000年以上も前の紀元前から行われてきたとされている。日本でいえば、大みそかと秋祭りとお盆が合わさったような行事といえるだろう。
アメリカでは、ヨーロッパからの移民がこれらの風習を持ち込んだのが始まりであり、7月の独立記念日が終わり一息ついた8月からは、ハロウィーン商戦の様相である。悪霊から身を守るために始まった仮装を楽しむ点は日本と同様であるが、それ以上に「トリック・オア・トリート!」と言いながら子どもが家々を回りお菓子をもらう習慣が定着しており、地域の活性化から食農教育までその裾野はとても広い。
本号では、アメリカのハロウィーンと農業の関わりを紹介したい。
アメリカ経済とハロウィーン
ハロウィーンはアメリカ経済においても重要なイベントである。2024年の調査によれば、ハロウィーン関連の消費は約100億ドル規模(日本の10倍以上)にのぼり、そのうちカボチャの売り上げも数億ドルに達しているとされる。そして、農家にとっては単なる作物の販売だけではなく、観光や体験型イベントを通じた農外収入が非常に重要となっている。
ハロウィーンの象徴「ジャック・オー・ランタン」
ハロウィーンの象徴といえば、「ジャック・オー・ランタン」と呼ばれるランタン。カボチャを用いて作られたものが定着しているが、本来は、カブであった。今日の形で定着したのは、移民によってハロウィーンがアメリカに伝わった際に、アメリカではカブの生産量が少なくカボチャの方が入手しやすかったり、カボチャの方がくり抜きやすくロウソクを入れやすかったりしたことが理由とされている。
アメリカの農家では、夏の終わりから秋にかけてカボチャの栽培が最盛期を迎える。ハロウィーンのジャック・オー・ランタン用のカボチャは特に大きく、形や色がそろった品種が人気である
アメリカの農場におけるハロウィーン
アメリカの各地の農場は春にはイチゴ狩り、夏にはブルーベリー狩りなど季節ごとにイベントを催しているが、毎年秋には「パンプキンパッチ(Pumpkin Patch)」と呼ばれる観光イベントを開き、家族連れや観光客で大変にぎわっている。そこでは、パンプキンショーケース(Pumpkins Showcase)という自らカボチャを選ぶ体験をしたり、ヘイライド(Hay Ride)という干し草の載ったトラクターに乗る体験をしたり、コーンメイズ(Corn Maze)というトウモロコシ畑の巨大迷路を楽しんだりする。
これらは、農業体験の場としても非常に人気で、子どもたちは農場で季節の作物や動物と触れ合うことで、食や自然への理解を深めるだけでなく、地域の農家と住民をつなぐコミュニティーの場としても機能している。
農業と行事の関係性
アメリカではハロウィーン(行事)が農業生産や販売形態を決定づけ、収穫体験・迷路・装飾展示など「アグリツーリズム」と結びついて農家の収益源になっている。日本においても、行事と農産物が結びつく例(正月ともち米、節分と大豆など)はあるが、これらは長い伝統の中で定着した消費スタイルであり、観光農業的に農家の直接収益に結びつくことは限定的である。ハロウィーンに関しても日本では「スーパーでの売り場演出」が中心で、農村現場の観光や体験までつながっていない。
アメリカでは、文化が農業を支え、農業が文化を育てる関係にあり、文化イベントが農業経営モデルに影響を与えている。一方、日本は、文化需要はあるが、農業現場との直結は弱いといえる。今後日本でもパンプキンパッチのような行事文化とあわせた観光農業を導入すれば、一層の農業振興につながるのではないか。