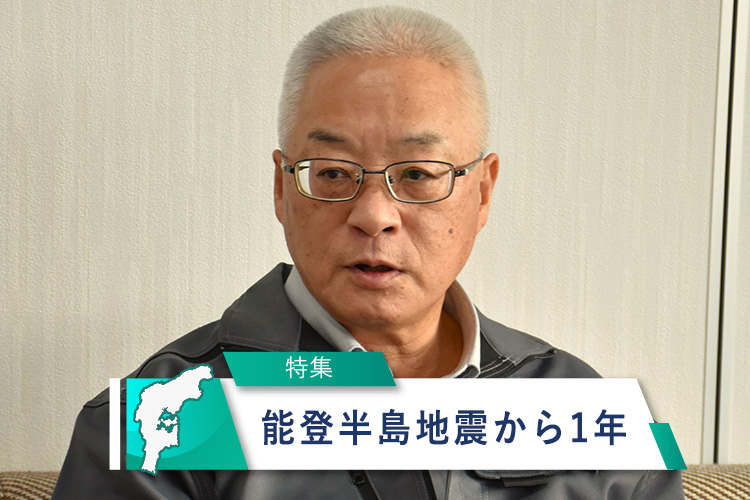能登半島地震から1年
【特集①】一歩一歩復興へ覚悟もって
石川県の奥能登地域を中心に甚大な被害が出た令和6年能登半島地震から1年が経ちました。9月には、再建の兆しがみえた被災地を記録的な豪雨が襲うなど、災害が続くこの間、被災地のJA役職員は、自らも被災者でありながらも、地域のくらしと農業の復旧・復興へ、死力を尽くしてきました。石川県のJA中央会やJA青年組織・女性組織も、それぞれの立場で支援を続けてきました。
この特集では、そうした各組織からのメッセージや取り組みをお伝えします。あわせて、震災直後から被災地取材を続ける日本農業新聞の記者より、これまでの被災地の姿を紹介します。
※この記事の最後に各特集へのリンクがあります。

“しびれる”光景 今も
強烈で悲惨な、“しびれる”ような光景がそこかしこにありますよ。それが、今の能登半島の現状です。幹線道路沿いを走るだけでは分からないと思いますが、現場に足を踏み入れるとその惨状が分かります。令和6年1月の地震で山がもろくなっているところに9月の大雨による水害です。山の大木が流され、土砂崩れも起きている。そうなったところにはもう住めないですよ。
建物の全損率は珠洲市と輪島市で約40%、東北や熊本の震災よりも悲惨な割合です。JAの施設の被害額は概算で約40億円に上ります。甚大な被害を受けた町野ライスセンターは、地滑りで修繕もできず建て替えが必要になりました。
9月の大雨で水に浸かった田んぼが900haほどあり、そのうち400haには流木や土砂が流れ込みました。令和7年の作付けの見込みもたたない状態です。管内では、未だに電気や水道が復旧していない地域もあります。工事がなかなか進まない現状に憤りはありますが、難しい問題です。
「復興センター」が稼働、ワンストップで営農再開を支援
こうした難しい状況ではありますが、一歩ずつ、歩みをすすめています。農業の復興に向けて自治体に働きかけ、「奥能登営農復旧・復興センター」の設置にこぎ着けました。本店内に設け、国や自治体と連携して、農地の復旧や営農再開に向けて農家を支援します。JAや県、農政局の職員が常駐し、基盤整備から融資までワンストップで相談ができます。
さらに、2t車クラスの移動購買車も導入しました。買い物難民になった住民の生活を支えようと、冷蔵庫、冷凍庫を備えた車に生鮮食品から雑貨まで幅広くそろえ、管内2市2町を巡回しています。
また、町野支店の敷地を輪島市に売却しました。町野地区は、被害が大きかった地域です。災害公営住宅建設のため、まとまった土地を探していた市から打診があり、組合員・地域住民の復興支援につながればと協力しました。
JAグループのさまざまな支援に感謝
地震発生後、全国の皆さんにたくさん応援をいただきました。これまで、あまり接点のなかったJAからも多くの支援をいただいたことには感激しました。JAグループの他、生協や市場などにも支援いただき、お見舞金は3億円ほどにもなりました。大変感謝しています。
震災直後、朽ち果てた家が並ぶ街並みを目の当たりにしたとき、「この地で再びJAがやっていけるのか」というのが正直な思いでした。JAの根幹をなす農家組合員、そして職員がいないとJA運営は成り立ちません。被災した職員は、これまで必死に復興のために毎日を過ごしてきました。これから組合員と営農再開に向けて覚悟を持ってお話をしていくことになります。ようやく復興に向け歩み始めたところですが、一歩一歩やっていくしかないと思います。能登半島は農業を中心とした地域です。JAが復興を引っ張り、地域の皆さんの役に立つときです。
RANKING
人気記事ランキング