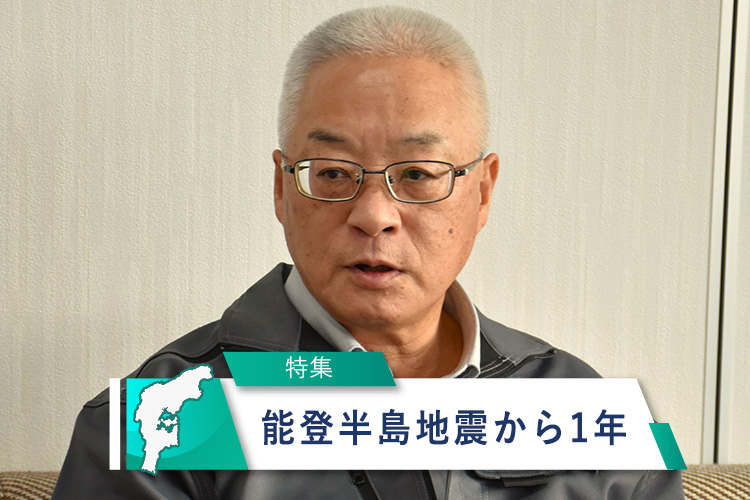能登半島地震から1年
【特集③】令和6年能登半島地震からの復旧・復興に向けたJAグループ石川の取り組み
石川県の奥能登地域を中心に甚大な被害が出た令和6年能登半島地震から1年が経ちました。9月には、再建の兆しがみえた被災地を記録的な豪雨が襲うなど、災害が続くこの間、被災地のJA役職員は、自らも被災者でありながらも、地域のくらしと農業の復旧・復興へ、死力を尽くしてきました。石川県のJA中央会やJA青年組織・女性組織も、それぞれの立場で支援を続けてきました。
この特集では、そうした各組織からのメッセージや取り組みをお伝えします。あわせて、震災直後から被災地取材を続ける日本農業新聞の記者より、これまでの被災地の姿を紹介します。
※この記事の最後に各特集へのリンクがあります。
県内死者500人超 農地や施設にも甚大な被害
令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」により、県内で500名を超える死者(災害関連死含む)※のほか、多くの負傷者、家屋の倒壊、土砂流入による道路崩壊、長期間にわたる断水、顕著な液状化が発生し、本県では未曾有の大災害となりました。
さらに、ライフラインの回復やインフラ整備等が進み、日常を取り戻そうしていた矢先の同年9月には、奥能登を襲う記録的豪雨により土砂崩れや河川氾濫、農地の冠水や流木等の侵入など大規模な被害が発生、被災地の復旧・復興に水を差す災害となりました。
農業面では地震により、農地や用排水路、農舎・畜舎等の生産関連施設が損壊したほか、豪雨では奥能登地域を中心に米や園芸作物の被害、再取得した農業機械が損壊したことで、農業者の農業再開への意欲減退や地域を離れる組合員が増加し、能登地域における農業生産力の維持や農村集落の存続が危ぶまれる状況となっています。
一方、JAの各店舗・営農経済施設等においても甚大な被害が発生したほか、信用・共済事業では、組合員の預貯金払い出しや家屋の査定業務対応等に追われ、十分な渉外活動ができないなど、今後の円滑な事業展開と経営収支確保に向けて懸念が生じています。
※令和6年12月24日時点
JAグループ石川と行政が一体となった復旧・復興支援
JAグループ石川では地震ならびに奥能登豪雨の発災直後に「JAグループ石川災害対策本部」を設置し、中央会・連合会や関連会社等が連携し、被害状況等の情報収集・共有、支援物資の提供、事業再開・運営等に関する支援の取り組みを行いました。
発災後、組合員・利用者からの信用事業や共済事業に関する各種相談ならびに被災JAへの取次業務を行うため「組合員・利用者総合相談センター」を設置したほか、農業者の営農相談や補助事業の申請支援のため県内6カ所に「農業者現地相談窓口」を設置、11月には地震と豪雨で被災した農業者をJAと行政がワンストップで支援する「奥能登営農復旧・復興センター」を設置するなど、被災者に寄り添った支援を実施しています。さらに地震や豪雨被害による農業者、JA施設の復旧支援を目的に「JAグループ支援隊」を結成し、JAグループ石川の役職員によるJA施設等の復旧作業支援を行いました。
また、JAグループ石川による要請集会を開催し、被災JA組合長から県選出与党国会議員に対して現場の窮状を訴えたほか、能登半島地震からの早期の復旧・復興、農業者が前向きに営農継続に取り組めるよう国・県に対する要請活動を実施しました。
地域のくらしと農業の再建へ被災地に寄り添った支援を継続
地震や豪雨で被害の大きかった能登地域は、過疎化・高齢化、担い手の減少といった既存の課題に加え、震災による地区外避難等による人口減少の加速、地域コミュニティの崩壊、組織基盤の縮小・弱体化など新たな課題にも直面しており、一刻も早い復旧と併せて地域農業の安定とJAの持続的発展を見据えた復興プランづくり、その実践が急務となっています。
このため、JAグループ石川の第40次基本戦略(2025~2027年度)においても第1の柱に「能登半島地震・奥能登豪雨からの復旧・復興」を掲げ、(1)JAグループの総合力発揮による「農業再建」支援、(2)地域インフラ機能発揮による「くらしの再建」、(3)被災地JAの経営再建に取り組むとともに、組合員や地域住民のニーズを汲み取り、寄り添う活動を通じ、1日も早い復旧・復興に向けてJAグループ石川が全力で取り組むこととしています。