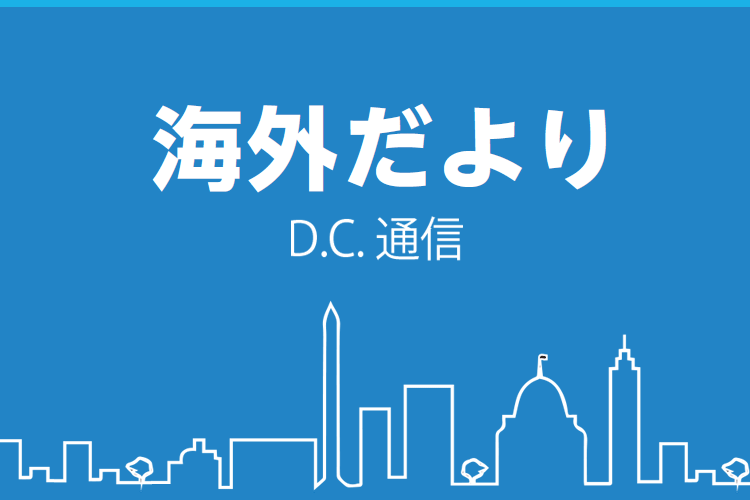本年1月号のこのコラムでは、近年の干ばつの影響により、昨年のアメリカの短・中粒種米の生産量がほぼ半減したこと、そしてこの干ばつの影響は当面続く可能性が高いという予測があることをお伝えした。
しかしどうやら、少なくとも本年においては、この予測は外れそうだ。この冬、主産地であるカリフォルニアが異例の大雪に見舞われたのである。
米農家を訪ねて
まだ肌寒さが残る3月上旬、カリフォルニア州サクラメント近郊の、ある米農家を訪問することができた。
彼の農場はサクラメント市中心部から北に車で1時間程度の場所に位置している。道路沿いにある農場の看板・門から彼の事務所まで、圃場に挟まれた私道を進むこと約3km、アメリカの農業の規模の大きさには常に驚かされる。
彼の農場は家族経営で、H-2Aビザ(季節農業労働者向けビザ)を活用して外国人労働力を雇用しつつ、通常年は2,000エーカー程度(約809ha)の面積で米を生産している。意見交換後に案内していただいた農機小屋には、CLAAS社の600馬力のコンバイン(ヘッダー込み1台約100万ドル)が2台鎮座していた。
昨年の干ばつの影響を尋ねたところ、水の供給制限により、通常の面積の4割程度しか米の作付けができなかったとの回答があった。しかしこれでもまだ彼の農場は恵まれていて、それは代々受け継がれている有利な水利権があり、優先的に水が供給されるためである。水源が異なる近くの地域では、昨年全く水が供給されなかった米農家もいるとのことであった。
また、彼の地域の土壌は重粘土質であるため他の作物の栽培が難しく、米の作付けができない圃場は休耕せざるを得ないとのことであるが、作物保険に加入していれば、水不足で作付けできなかった部分も一定の補償を得ることができ、さらに供給不足によって短・中粒種米の価格が上昇したことから、生産できた米は高値で販売することができ、経営としては通常年よりもむしろ良かったとのことであった。彼は、「干ばつの影響で米が生産できなかったとしても、作物保険のおかげで、廃業する農家はほとんどいないだろう」と話している。
今年の生産見込みについて尋ねたところ、冒頭に触れた大雪の話を伺うことができた。彼の農場がある地域は、雪解け水が流れ込む貯水池から水を引いて米を栽培しているが、冬季の異例の大雪により、その貯水池が6~7年ぶりに満水になり、源流となるシエラネバダ山脈にも大量の雪がまだ残っているとのことであった。周辺の米農家を含め、今年は全ての圃場に米を作付けできる見込みであり、カリフォルニア州全体で見ても、平年程度の作付面積にまで回復するのではないかといわれているそうで、彼はむしろ、供給量の回復に伴う米価の下落を懸念している。 これらはすなわち、米国産の価格上昇や円安の影響で縮まった米国産米と日本産米との価格差が、再び拡大する可能性を示している。
この他、生産コストの上昇や労働力(特に、高度化・複雑化した農機を操作できる熟練した労働力)の確保などが大きな課題となっているという話や、次期農業法に対する要望などさまざまな話を伺うことができたが、水田からのメタン排出削減対策については日本とは全く異なる認識で、興味深かった。すなわち、彼らは水を張ることによる生物多様性などへの効果を重視しており、中干し期間の延長などには否定的であった。水の価値の違いは、こうしたところにも表れているのかもしれない。

訪問した農場の門からの景色(筆者撮影)