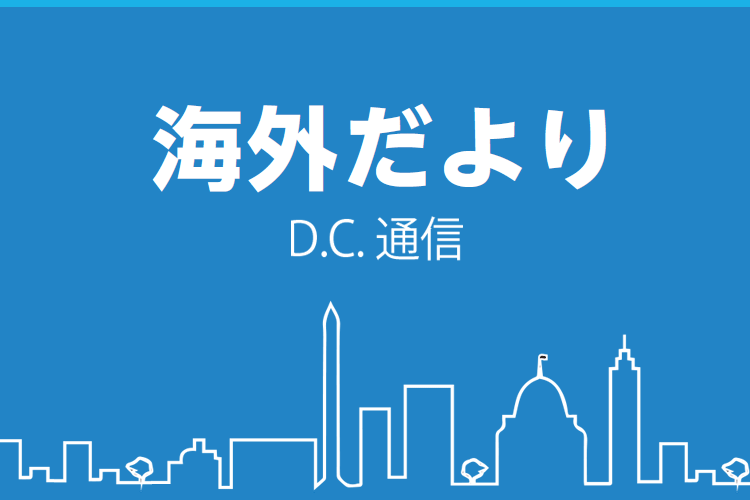Wagyu農家を訪ねて
「和牛」は日本固有の肉専用種であるが、和牛をルーツに持つ「Wagyu¹」の生産は世界中で行われている²。本年夏、アメリカのWagyu農家を訪問する機会を得たため、筆者が訪問したWagyu農家の概要を簡単にご紹介したい。
初めに、ノースカロライナ州の「Wilders Wagyu」をご紹介したい。Wagyuの生産を開始したのは2020年で、現在は肉用150頭、繁殖用300頭程度のフルブラッド(和牛遺伝資源100%)Wagyuを飼養している。Wagyuは現在27~29か月齢で屠畜し、筋肉内脂肪含量(IMF)は30~40%程度である。農場従業員によると、肥育期間を延ばせばIMFが40~50%になるかもしれないが、ステーキで食べるには脂肪が多すぎるため、IMFが30~40%の牛肉を25~26か月で仕上げることを目標にしているとのことであった。Wagyu肉の販売の約8割はオンラインで、その他は農場併設のミートショップや地元のファーマーズマーケットで販売している。経営の主な収入源は牛肉販売であるが、バイオテクノロジー企業であるVytelle社と提携してWagyu遺伝資源の国内外への販売にも取り組んでいる。農地面積は約2,000エーカー(約809ha)。


続いてご紹介する「Traber Ranch」も2020年からWagyu生産に取り組んでいる。製薬会社に勤める農場主の父親が日本で働いていた際に和牛に興味を持ったことがWagyu生産を始めたきっかけで、バージニア州に約550エーカー(約223ha)の土地(主に森林)を購入し、自ら伐採して放牧地等を造成した。現在の飼養頭数は110頭程度で、農場の近くの町に所有する直売所兼レストランでWagyu肉を販売している。日本のA5和牛のサシが目標で、現在は32~36か月で屠畜しているが、試験的に38か月齢まで育てている牛もいる。ステーキで食べるには和牛のサシは多すぎるとの意見に対しては、少量で満足できるのが和牛の特徴であり、IMFが少ないWagyuとは味わいも全く異なると農場主は語っていた。


次にご紹介するバージニア州の「Wagyu Shimizu」は、アメリカ人の夫と日本人の妻が経営する農場で、農場名“Shimizu”は妻の姓に由来する。アメリカ人の夫がWagyuの収益性の高さに注目し、2014年に最初のWagyuを導入した。現在は約30エーカー(約12ha)の農地で、フルブラッドWagyuと交雑Wagyuを計40頭程度飼養している。2023年に屠畜したWagyuは全てIMFが40%以上、最高62%を達成し、Wagyuステーキの肉質を競う「Triple Crown Steak Challenge³」では同年の総合優勝に輝いた。ステーキ用だけでなく、薄切りWagyu肉の普及にも努めている。なお、農場主の本業はフードディストリビューターである(現在はほぼリモートワーク)。


最後にご紹介するバージニア州の「Twin Oaks」はもともとアンガス牛の生産に取り組んでおり、2016年に最初のWagyuを導入、現在は約225エーカー(約91ha)の農地で計100頭程度飼養している。フルブラッドWagyuは27~30か月齢、交雑Wagyuは24か月齢程度で屠畜し、牛肉はオンラインおよびファーマーズマーケットで販売している。販売に際して、MIJカメラ(枝肉撮影用カメラ)でIMFを測定し、40%以上のものをBlack Labelとして独自にブランド化、同農場における通常のWagyu肉(IMF30%強程度)よりも高い価格で販売している。なお、農場主の本業はビルの建設会社勤務である。


今回訪問したのはノースカロライナ州とバージニア州の数軒のWagyu農家であったが、Wagyuに対する考え方や規模は各人各様で、多様なWagyu生産が行われていることが分かる。肉用牛生産に占めるシェアはまだごくわずかであるが、アメリカにおけるWagyu生産が今後どのような展開を遂げるのか、注目しておく必要があるだろう。
1 日本の和牛の遺伝子を持ち海外で生産されている肉用牛を「Wagyu」と表記する。
2 世界のWagyu生産は1998年以前に海外に渡った和牛遺伝資源が基になっており、その後の和牛遺伝資源の輸出実績はなく、和牛遺伝資源は現在厳しく管理されている。なお、世界におけるWagyu生産の動向は、JA全中発行の国際農業・食料レター2023年12月号「世界のWagyu最前線 -孤高の和牛と繋がるWagyu-」等を参照。
シェフ向け和牛セミナー
続いては「和牛」に関する話題である。10月21日から23日にかけ、在アメリカ日本国大使館において和牛セミナーが開催された。このセミナーはワシントンDC在住の現地シェフを対象とし、アメリカでの和牛の普及促進等に取り組む和牛ソムリエ(Wagyu Sommelier⁴)と日本国大使館等が企画・運営した⁵。
トップシェフと呼ばれるようなシェフも参加する中で、参加者らは、和牛の基礎知識から始まり、和牛のさまざまな部位の活用方法、レストランでの提供実例、カット・調理の実演、メニュー開発に関するワークショップ、和牛を用いた調理実習等を通じて和牛に対する理解を深めた。また、セミナー終了後には修了証の授与も行われた。セミナーに参加したシェフたちからの評判は上々であり、アメリカの首都で和牛の魅力が今後さらに広まっていくことを期待したい。
12月に入り、これからクリスマスや年末年始が控えている。ちょっとした特別な日には、“本物の和牛”をぜひご賞味いただきたい。
5 なお、本セミナーの和牛調理実演等用として、今回は佐賀牛が提供された。