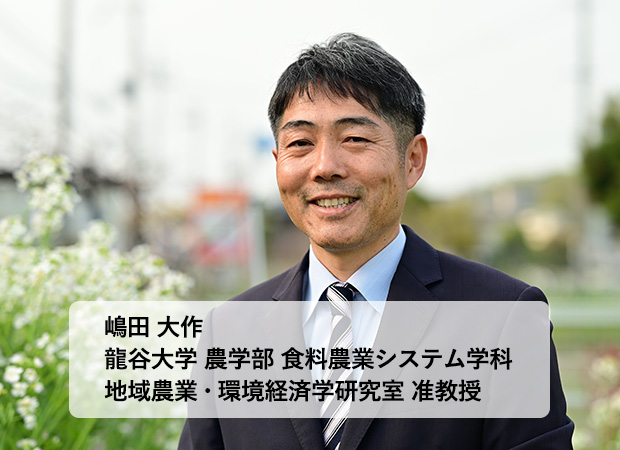食・農・地域の未来とJA
外部人材の確保・育成に向けた特定地域づくり事業協同組合の可能性
重要性が増す新規就農における外部人材
農業の担い手の量的減少と質的低下(高齢化)が進むなかで、早急に取り組むべきことは次世代の担い手を確保・育成することである。しかしながら、2020年の農林業センサスによれば、後継者を確保していない農業経営体は7割に及ぶことから、農業内部だけに頼った人材確保は極めて厳しい状況にある。したがって、農業内部のみならず、農業外部からも幅広く人材を確保することが農業の担い手対策として重要な取組課題となる。
外部人材の確保に関して、農林水産省が公表している「新規就農者調査」をみると、2021年の新規就農者は52,290人(A)であり、このうち主に外部人材で構成される新規雇用就農者と新規参入者は合わせて15,400人(B)となっている注1)。新規就農者に占める外部人材の割合(B/A)は29.5%であるが、49歳以下の新規就農者に限定した場合、外部人材の割合は61.0%へと跳ね上がる。青年層の新規就農者の過半を占める外部人材は、次世代の担い手として重要な存在になっているといえよう。
特定地域づくり事業協同組合による外部人材の確保・育成の特徴
外部人材は新規就農するにあたり、研修時や就農後の資金として農業次世代人材投資資金を活用できるが、その金額水準は経営・生活のすべてを賄えるほどではない注2)。他方、受け入れ側が外部人材に対して研修を行う場合には、指導・教育にかかる費用が発生する。新規就農や受け入れに必要な費用を工面しながら、効果的に外部人材を確保・育成する必要がある。
この点に関して注目されるのは、2020年6月に施行された特定地域づくり事業協同組合制度である。これは地域産業の事業者(組合員)で構成される組合が職員(無期雇用職員に限定)を雇用し、時期に応じて組合員のもとに職員を派遣する制度である。当該職員は給与や社会保険等が保証されたうえで、様々な組合員のもとで働きながら各種技能を習得する。一方、職員を受け入れる組合員は利用料金を支払うものの、繁忙期等の人手不足を解消することが可能となる。組合の運営経費は組合員からの利用料金と公費助成が充てられる。
こうした特定地域づくり事業協同組合は全国で89組合あり(2023年6月時点)、このうち組合員のなかに農業者がいる組合は72組合と8割を占める。なかでも組合員が農業者だけで構成される組合注3)は新規就農における外部人材の新しい受け皿となりうる。ここでは様々な農業者のもとに無期雇用職員として外部人材が派遣されることから、外部人材は長期間にわたって営農技術を幅広く身につけることができる。また、農業者である組合員のネットワークを頼って、新規就農に必要な農地等の経営資源の情報を収集することも可能となる。さらに、派遣事業を通じて地域に顔が売れるため、地域との信頼関係を構築することにもつながる。このように、多様な農業者が組織的に外部人材を支援する方法は、既存の外部人材の受け皿(先進農家や農業法人、農業公社、農協出資法人など)にはみられない特徴である。
特定地域づくり事業協同組合の課題とJAの役割
しかし、職員をローテーションで組合員(農業者)に派遣する日常業務では、契約書の作成をはじめとする煩雑な事務作業が発生する。また、派遣職員の稼働率(派遣先での年間労働時間/[年間総労働時間+年間総休業時間])が8割未満の場合は公費助成が減額される。稼働率を上げるには派遣職員の通年雇用が必要になるが、組合員が農業者のみの場合は農閑期の雇用が課題となる。今後は、事務作業の効率化を図るとともに、組合員に6次産業化を促し、農産加工事業や販売事業へ職員を通年で派遣できる体制を整えていかねばならない。
このように、農業に特化した特定地域づくり事業協同組合では、農業特有の複雑な作業工程や季節性に対応するため、事務局の役割が重要になる。事務局は、そのほかにも派遣職員の労務管理や会計なども行うことから、どのような主体が事務局を担うかが組合運営上のポイントとなる。この点に関してJAは農業者との調整や作業工程管理、会計等の業務に長けており、実際のところ、特定地域づくり事業協同組合の事務運営にかかわるJAもみられる。
特定地域づくり事業協同組合の運営を通じ、外部人材の確保・育成に取り組むJAが今後増えることに期待したい。
注1)新規雇用就農者と新規参入者のそれぞれには、農家子弟が一部含まれる。
注2)農業次世代人材投資資金には、就農準備資金(年額150万円・最長2年間)と経営開始資金(年額150万円・最長3年間)がある。
注3)農業者(もしくは農業関係者)だけが組合員となっている特定地域づくり事業協同組合は2023年6月時点で4組合存在する。