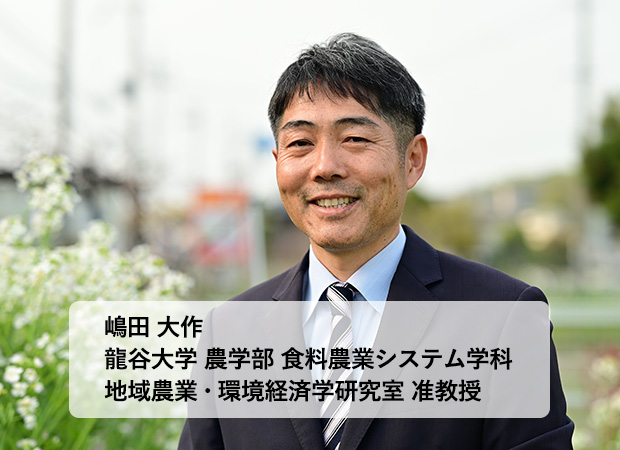食・農・地域の未来とJA
農業の持つ可能性について
昨年から小中学生を対象とした「『ごはん・お米とわたし』作文・図画コンクール」(JA全中主催)の図画部門の審査会委員長に就任しました。全国から応募してきた子どもたちの作品を見ると、観察力の鋭さ、大人には描くことのできない絵に感動するとともに、未来と希望を感じます。
このコンクールは今回で第48回となります。応募者の中には親子3代で作品を応募しているご家庭もあると聞き、あらためて歴史の重みを実感しますね。
人生の原点は農業にある
私は滋賀県の兼業農家の生まれです。子どもの頃は休みの日に農作業の手伝いをしていました。
大学は文系の学部に進みましたが、サークル活動では「農村問題研究会」に入りました。農業実習で群馬県の嬬恋村に「援農」に行ったのですが、そこでは毎日の農作業の中で農家の方をはじめ周囲とコミュニケーションをとりながら信頼関係を築いていく。農業経営の実態を調査・分析し、課題を掘り下げ、大学祭で発表しました。
このような頭だけでなく身体を動かして現場を足場にし、具体的な事実に切り込んでいく手法は、私の教育評論家としての思想・方法論の土台になっています。
私の人生の原点は農業にあるのです。
農業は子どもを育ててくれる
よく「子どもが成長する過程で、食や農はどのような影響を与えるのでしょうか」と質問を受けますが、私の教師時代、岩手県に修学旅行で田植えをしに行ったことがありました。田植えだけでなく、地域の文化も学ぼうといろいろな仕掛けをしました。東京から岩手県に田植えをしにやって来るというのが話題になって、地元のテレビ局が取材に来てくれたりもしました。
その当時は、学校が荒れていた時代です。クラスの中には「何で田植えするために、わざわざ岩手県まで行かなきゃならないんだ!」と文句を言う非行の子たちもいて、不安もありましたが、いざやってみたら、泥だらけになるまで一番喜んで頑張っていたのはその文句を言っていた子どもたちだったんです。他の学校でも同様でしたが、農家と協力して授業の中に農業体験を取り入れてみると、それまで荒れていた学校が一気に落ち着いてくる。もう不思議なくらいにです。
農業高校に視察に行くようになって思ったことですが、生徒の目が輝いているんですね。
一人二人だけじゃない、1学年300人ならその全員の目が。これは一体、何でなんだろうと。
それは、彼らは学校生活の中で「いのち」と向き合っているからなんですね。彼らは自らの育てる野菜、果樹、花卉、家畜という「いのち」を常に相手にしているからです。
埼玉のある高校へ行ったとき、ブドウ園があって「この木は○○君の担当」って札がかかっている。担当の先生に聞いたら「このブドウ園を責任担当している生徒はいつも午後6時、7時くらいまで作業している。剪定
、摘果、袋がけ等、収穫から販売まで全て責任を持って担当していますよ」というお話でした。
私がもう一つ審査委員長を務める「全国高校生 農業アクション大賞」でも、大賞を受賞した山形県の村山産業高校のサトイモの早期栽培の事例(4月号「若者がみつめる農・食」で掲載)など、大人では思いつかないことに若い人たちは挑戦し、実践してしまいます。発想が豊かな若者たちは、科学を駆使してとんでもないことを考えついてしまう。
このようなことからいえるのは「農業は子どもを育ててくれる」ということです。
私の持論ですが、普通高校でも1学年に7~8時間、理想を言えば10時間くらいは農業実習を入れるべきですよ。その中で生きることの意味をしっかりと学び、その先に進んでもらいたいですね。エリートを目指すのは素晴らしいことですが、他人を蹴落として自分がのし上がるのではなく、問題を解決するために探究し、日本の将来を背負っていく、そういうビジョンを持ったリーダーになってほしいと願っています。
JAグループだからこそ伝えられること
「食育」という言葉がありますが、JAグループは「食農教育」という独自の活動を展開していますね。この言葉には大きな意味があります。食べる前には作らなければならない、そのためには農が必要であることをしっかり伝えているのですね。
JAグループからも「学校の授業に農業の時間を入れるべきだ」というご意見があるようですが、これはぜひとも実現したいことです。関係省庁にも働きかけていきたいですね。全国のJAは「バケツ稲」や農業体験、親子料理教室、学校への食材の提供等、地域の食農教育に積極的に取り組んでいます。たいへん力強く、ありがたいことです。
異常気象や自然災害等、このままだと地球が壊れてしまうのではと思われるような状況の中で、食べるということ、それを生み出す農業は、どこの国の人たちにとっても生きる上での基本中の基本です。このことを国民がどのように考えていくか。まずは自分の国で消費する食料は、できるだけ自分の国で生産しようという、JAグループが提起されている「国消国産」を進めていくことです。この役割を担えるのはJAしかありません。
JAグループの皆さんにお伝えしたいことは、ぜひ、自分たちのやっていることはみんなから求められていて、責任は重大であるということを認識して、いろいろな分野に働きかけたり、さまざまな形でアピールをして、日本の食と農をしっかり守っていただきたい。
私も教育の領域から皆さんを応援していきますよ。
まずは食料自給率50%以上を目指して一緒に頑張っていきましょう。