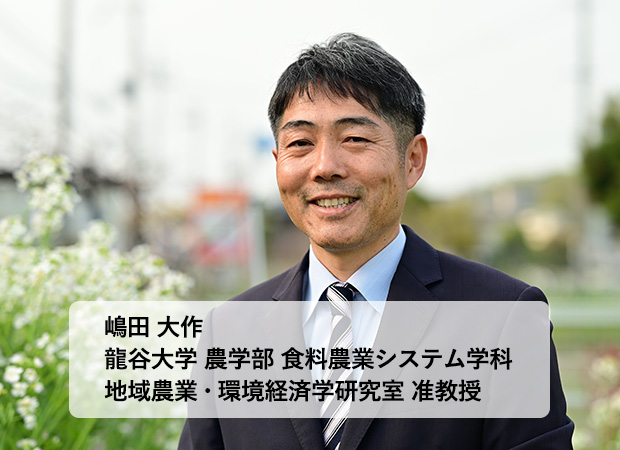食・農・地域の未来とJA
ごちゃまぜの居場所で地域のつながりを
なぜ、全国で「こども食堂」が増え続けているのか?
保育園も閉園、小学校も閉校となった北陸地方のある地区(世帯数500)で、地元の方たちによるワークショップを見学したときのことだ。住民の方たちが「自分でできること」として「食堂・カフェの運営」を挙げていた。
地域がさびしくなり、「消滅」という言葉が頭をよぎるようになった。地域全体が高齢化し、ひとり暮らしが増え、空き家が増え、商店街はシャッター通りとなり、自治会はかつてほど活動していない。それでも人は生きているかぎり、つながりを求める。大企業誘致は自分でできる気はしないが、食堂やカフェなら自分たちでもできるかもしれない。そしてそういう場所があれば、地域のお年寄りやこどもたちが立ち寄ってくれて、ささやかなにぎわいをつくり、つながりを維持できるかもしれない…。そのように考える人たちが全国に何万人何十万人といて、その一部が実際に食堂やカフェを立ち上げ、その一部が「こども食堂」と名乗る。こども食堂はそうやって増えてきた。
私たちが統計を取り始めた2018年以来、コロナ禍を含めて、毎年1,000箇所以上増え続けた。昨年は過去最大の1,700箇所増で、全国の公立中学校数に並んだ。ほとんどすべてが自前のボランティア活動である。
一円の得にもならない活動を、毎年これだけの人たちが、絶えることなく全国津々浦々で立ち上げ続けているということは、裏を返せば、それだけ多くの人が抱く強い危機感があるということだ。それは地域コミュニティの衰退であり、つながりの欠如だろう。
「ごちゃまぜ」の多世代交流、世代間交流の場となる「こども(きっかけ)食堂」
地域コミュニティの衰退、つながりの欠如と言えば、問題が大きすぎて何から手をつけていいかわからない気がしてくるが、求められているのは特別なこと、大それたことではない。
80代のお年寄りが朝の庭仕事の最中、ふと「私が今ここで倒れたら、いつ誰が見つけてくれるだろう」と思って不安になる。そのとき頭に思い浮かぶご近所のあの人この人がいれば、気を持ち直して作業を続け、気持ちよく朝食に向かい、おいしく食べられる。誰も思い浮かばなければ不安なまま過ごし、朝食もおいしく感じられなかったり食べられなかったりする。そうやって徐々に生活の質(QOL)が低下していき、鬱々とし、閉じこもりがちになり、生きていても楽しいことなんかない、と感じるようになる。「ご近所のあの人この人」が思い浮かぶかどうか。地域の人たちと顔を合わせる機会があるかどうか。気軽に立ち寄れる場(居場所)があるかどうか。それは、手近な生活圏域で、2−3人の仲間がいれば、手をつけることのできる課題だ。
なくなってきた、減ってきたから、自分たちがつくる。自治会の集いはともすると敷居が高いから、もっと敷居の低い場所をつくる。こどもが走り回っても疎まれない場所をつくる。こどもと高齢者が交流できる場所をつくる。保護者が子育てから一瞬離れて、一息つける場所をつくる。女性が男性に遠慮しなくてもいい場所をつくる。そうやって、ささやかでも、ほっとできてつながれる場所をつくろうとする人々の営みが積み上げられてきた。
こうした経緯でできていくのがこども食堂なので、当然「こども(専用)食堂」は少ない。約8割のこども食堂はこどもも大人も、所得にかかわらず参加できる「こども(きっかけ)食堂」であり、「ごちゃまぜ」「まぜこぜ」の多世代交流、世代間交流の場だ。松重豊さんが登場するテレビCMのセリフを借りれば「あなた食堂」だ。そのテレビを見ているのが誰であれ、こども食堂に参加できる。
よってこども食堂が増えていくということは、誰でも参加できる地域の居場所が増えていくということである。それが公立中学校と同じ数になったが、まだ少ない。これが小学校と同じ数になり、さらにそれを超えて投票所と同じ数になれば、どこに住んでいる人に対しても「歩いていけるあなたの居場所がありますよ」と言える状態になる。私たちはそれを目指している。
高齢化が進み、こどもが減り、めったに人の歩く姿を見かけなくなっても、いついつあそこに行けば地域の人たちと会えますよ、と言える状態になる。移住者や外国籍の人が地域の情報や慣習を知らなくても、あそこに行けば、食事しながらの雑談の中でゴミの出し方とか病院のこととか、ちょっとした地域のお得情報とか教えてもらえますよ、と言える状態になる。私たちはそれを目指している。
それは工場や施設のような、目に見えるハコモノではない。住民の、住民による、住民のための、ささやかで身の丈に合った取組みだ。しかしそれゆえに生活者としての実感に基づいた、地に足のついた取組みとも言える。
コミュニティの衰退をみんなで支え、地域を次の世代につなげる
昨年、私の主宰するNPOむすびえで、全国のこども食堂の運営費を試算したところ、全国9,132箇所のこども食堂は総額73億円で回っているという推計が出た。対象としたのは会食形式の住民交流活動で、食費、場所代などの現金支出に加えて、寄付でいただいた食材なども現金換算した結果だ。うち行政からの補助金は10億円だった。つまり63億円は民間のさまざまな人たちの支え合いで回っている。
農家さんやJAの各支部が規格外野菜を持ってきてくれる。地元の事業者が場所を貸してくれる。商工会やロータリー・ライオンズなどが寄付してくれる。地元のスーパーチェーンが食品リサイクル対象商品を寄付してくれる。ナショナル企業・グローバル企業が資金支援や物品提供をしてくれる…。こうしたことの積み重ねでこども食堂は運営され続けており、現場からは「気づいてみたら、始めてから一度も米も野菜も買わずに済んでいる」という声をしばしば耳にする。コミュニティの衰退をみんなで支える地方創生のモデルケースがここにある、と感じる。
少子化も高齢化も人口減少も簡単に歯止めはかからないが、こども食堂のような多世代交流の場をハブに各種資源の地域内循環が促進され、人と人のつながりがなんとか保たれていくならば、私たちの地域と社会の持続可能性はまだなんとかなるかもしれない…私はそんなふうに夢想している。より多くの人が、地域を次の世代につなげるためにという思いで、こども食堂のようなごちゃまぜの居場所をともに支える仲間になってくれることを切に願っている。