理事による「ふるさと農業授業」の展開
教育文化事業部では、地域の中でJAに魅力を感じる人、いわゆる「JAファン」づくりにも力を入れている。特に、次世代のファンづくりを意識しており、そのために実施している取り組みの一つが理事による「ふるさと農業授業」である。
2023年10月17日、管内のある小学校の5年生を対象として、同JAの中野和彦理事(当時)による出前授業が行われた(写真2)。
「農業って何だと思う?」の質問からスタートし、地元の農業の歴史と現状が、自身の体験談を交えながら伝えられた。また、食品ロスの問題などについても取り上げ、同理事の言葉に子どもたちは真剣に耳を傾けた。
終了後、子どもたちからは「地域で協力して農業に取り組むのは良いことだと思った」「食べ物がたくさん捨てられていることに驚いた」といった声が聞かれた。一方、中野理事は、「子どもたちが最後まで熱心に話を聞いてくれてうれしかった。授業を通して食べ物を大切にする心を持ってもらいたい」と話している(日本農業新聞、2023.10.21の記事を参照)。

JAこうかのふるさと農業授業は、同JAの池村正代表理事組合長が甲賀市・湖南市の教育長を訪問し、食農教育の促進を要望する中で実現したものである。管内すべての小学校での実施とはなっていないが、2023年度の場合は中野理事を含む3人の理事によって4校の5年生を対象に行われている。
教育文化事業部では、地域の子どもたちにとってなじみの深い地元のおじさん・おばさんが、自らの経験や考えを、自らの言葉で伝えることが農業に対する関心や理解を深め、ひいてはJAファンづくりの一番の近道であると考えている。実際に授業の内容は、すべてそれぞれの理事が考えたものとなっている。
また、ふるさと農業授業の一環として小学校での田植え体験を実施しており、そこでの先生役を地元理事が務めることとしている。2024年度においては、管内10の小学校で開催され、多くの理事が子どもたちに優しく教えながら、ともに汗を流している。このように、同JAの食農教育においては理事が主体的に役割を果たしている。
『ちゃぐりん』を通じた学びの場づくり
JAグループでは、食農教育の教材の一つとして『ちゃぐりん』を活用している。
同誌は家の光協会が毎月発刊しているもので、「いのち・自然・食べ物・健康・農業」の大切さを小学生に伝え、思いやりと助け合いの精神を育むこと、さらには子どもたちの好奇心・探究心・創造力を喚起することを目指した誌面づくりが行われている。
さて、『ちゃぐりん』では毎年感想文を募集している。これは同誌7~9月号を読み、その感想を800~1,200字でまとめるものである。小学生にとってはなかなか労を要するものであることは容易に想定されるが、その分食や農について考えるよい機会となる。教育文化事業部では、管内のすべての5年生がこの感想文に取り組むことを目指すことにした。
そのためにまず、甲賀市と湖南市それぞれで月1回開催されている校長会において発言の時間をもらい、子どもたちの食農教育の教材として『ちゃぐりん』を活用することを提案した。次に、各支所長がそれぞれのエリア内の全小学校に出向き、『ちゃぐりん』のよさを説明するとともに、感想文に取り組むことを依頼した。そして感想文の募集が始まると、教育文化事業部が各小学校に出向き、すべての5年生に対して同誌の提供を行い、再度感想文の応募を依頼した(写真3)。
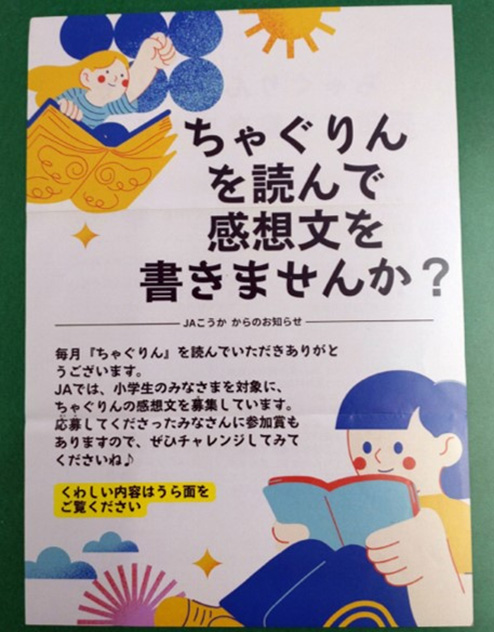
こうした働きかけの結果、管内の全5年生1,249人のうち、269人から感想文の応募があった。小学校によっては、夏休みの自由研究に位置づけてくれたところもあり、入賞作品も多数に上ったそうである。この感想文に真剣に取り組んだ5年生は、少なくなかったものと考えられる。
ところで、同JAは『ちゃぐりん』を感想文の教材としてだけ活用しているわけではない。早くから同誌を用いた農業体験、「ちゃぐりんキッズ倶楽部」に取り組んできている。そして2024年度に、その内容のリニューアルを図っている。従来は、小学生とその保護者を対象として、地域農業とJAへのつながりづくりをテーマとしていたが、2024年度からは「作る喜び」「食す喜び」「売る喜び」をテーマに据え、「農業」にとどまらず「農家」そのものを疑似体験することをコンセプトとして、全6回の活動の中に従来はなかった「売る体験」「マネー教室」を加えた。
参加した子どもや保護者からの評価は上々で、「楽しかった」「参加して良かった」といった声が多数聞かれている(写真4)。教育文化事業部では、同倶楽部での活動を通じて芽生えたはずである食や農に対する関心をさらに深めてもらうために、LINEや訪問活動を通じて継続的にコミュニケーションを図りたいと考えている。

“心”をつなぐ教育文化事業部
以上、本稿ではJAこうかの教育文化事業部による取り組みを見てきた。ここまで取り上げた取り組み以外にも、女性部員の拡大を目指した活動の見直し、くらしの活動を介した事業間連携の促進、JAこうか公式LINEの配信スタートをはじめとする広報活動の充実化など、さまざまな新しい動きが見られる。
教育文化活動とは、前述したとおり組合員や組合員家族、地域住民などとの関係性を築くための活動である。活動の成果は「関係性」、換言すれば組合員や地域住民の“心”をJAとつなぐことである。それを目に見える形で示すのは難しい。そしてそれゆえに、JAの中でしばしば軽視されることとなる。
しかし、“心”のつながりがない中での事業利用は、言ってみれば「取引」であり、価格をはじめとする条件次第でつながりは簡単に消えてしまうだろう。その一方で、“心”がつながっているならば、条件に基づいて対応を変えるのではなく、むしろ自分たちに望ましい条件を求めて、日常的に協力的な行動がとられるだろう。こうした行動こそが、地域に根ざした協同組合としてのJAに不可欠なものなのではないか。
教育文化事業部を統括する山城昭樹部長によれば、同部の7人は「JAこうかを変革しよう!」を合言葉として、職位に関係なく全員がプレイングマネージャーであることを認識して日々の業務に励んでいる。発足して約2年であるが、すでに多くの新たな取り組みや既存の取り組みの見直しが進められている。JAこうかにおいては、教育文化事業部の献身性が発揮される中で、すでに「変革」が起きつつあるといえるだろう。
RANKING
人気記事ランキング



